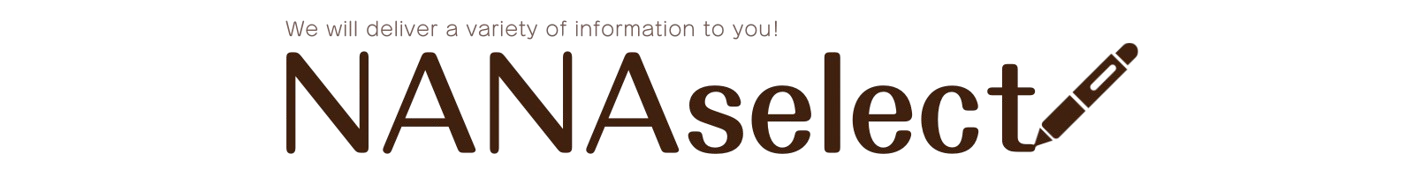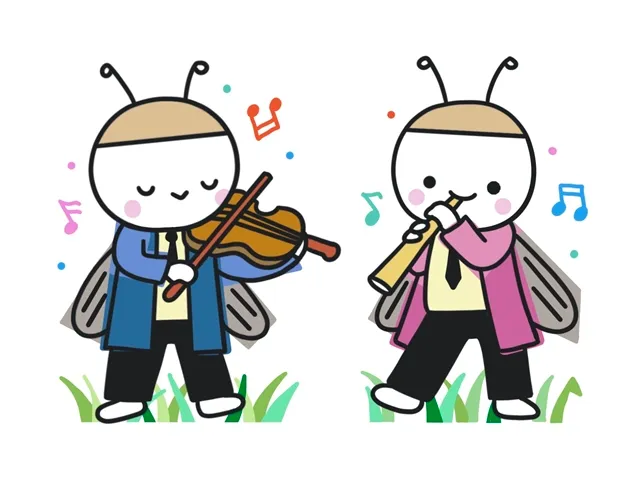秋の夜長に耳を澄ませると聞こえてくる、鈴虫やコオロギの澄んだ鳴き声。
実は、この風情ある音色をご自宅でも楽しめるのをご存じですか?
近年では夏の終わりになると、ペットショップやホームセンターで鈴虫やコオロギが販売されており、気軽に飼育を始められるようになりました。
とはいえ「どうやって飼えば鳴いてくれるの?」「お世話は難しいの?」と気になる方も多いはず。本記事では、
特に“鳴き声を楽しみたい人”に向けて、自宅で鈴虫とコオロギを上手に育てるポイントをわかりやすく解説します。
鳴き声を楽しむためのポイント

鈴虫やコオロギを自宅で存分に楽しむコツは、オスを中心に飼育し、安心できる快適な環境を整えることにあります。鳴き声を聞きたいなら、まずはオスを選ぶことが大切なんですね。
なぜオスを選ぶの?
「鳴くのはオスだけ」というのは意外と知られていないポイント。メスは静かに過ごしますが、オスは羽をこすり合わせて音色を奏でます。そのため、鳴き声を目的にするならオスは欠かせません。
快適に過ごせる環境のポイント
清潔で居心地の良い環境を用意すると、虫たちもリラックスして鳴いてくれます。
- ケースは広めで清潔なものを選ぶと安心。
- 底材には土や腐葉土を敷いて、乾燥しすぎないようにします。
- 掃除はフンや残りエサを毎日取り除くと臭いも少なくなります。
ちょっとしたお世話の積み重ねで、虫たちが元気に鳴いてくれるんです。
エサの工夫
エサは専用フードをベースにしつつ、野菜やタンパク源を少し足してあげるとバランスが取れます。
- 市販のフードで基本の栄養はバッチリ。
- きゅうりやナスなど水分のある野菜もおすすめ。
- 煮干しやかつおぶしを少し加えると元気さが増します。
「今日は何をあげようかな?」と考えるのも、飼育の楽しみのひとつですね。
鈴虫とコオロギの鳴き声の違い
実際に飼ってみると、鳴き声の違いにも驚きます。
- 鈴虫は「リーンリーン」と澄んだ音色で秋らしさを演出。
- コオロギは「コロコロ」「リーリー」と活発で元気な印象。
両方を一緒に飼えば、音色のハーモニーを楽しめます。夕方から夜にかけて鳴くことが多いので、静かな時間に耳を澄ませると、心がすっと落ち着いていきますよ。
このように、正しい環境とちょっとした工夫を加えることで、自宅でも秋の虫の合唱を思う存分楽しめるのです。
飼育に必要な環境づくり

鈴虫やコオロギを長く元気に育てるには、住まい作りがとても大切です。基本のポイントを押さえておくと失敗が少なくなります。
ケースの選び方
市販のプラケースや虫かごで十分ですが、フタ付きで通気口のあるものを選びましょう。大きめのケースならオス同士がケンカしにくく、鳴き声も響きやすいです。
底材とレイアウト
- 土や腐葉土を2〜3cmほど敷くと落ち着きやすい。
- 観察を重視するならキッチンペーパーでも代用可能。
- 小さな木片や石を入れると隠れ場所になり、虫が安心します。
温度と湿度の管理
- 最適温度は25℃前後。夏場は直射日光を避け、冬は室温に注意。
- 乾燥しすぎると弱るので、霧吹きで1日1回軽く湿らせるのが理想です。
掃除のタイミング
フンや食べ残しは放置すると臭いやカビの原因になります。2〜3日に一度はチェックして、必要に応じて取り除きましょう。
環境を整えることで、虫たちは安心して鳴き、私たちも気持ちよく観察や音色を楽しむことができます。
次は、エサや水分補給についてさらに詳しく見ていきましょう。
飼育に必要な環境づくり
鈴虫やコオロギを長く元気に育てるには、住まい作りがとても大切です。基本のポイントを押さえておくと失敗が少なくなります。
ケースの選び方
市販のプラケースや虫かごで十分ですが、フタ付きで通気口のあるものを選びましょう。大きめのケースならオス同士がケンカしにくく、鳴き声も響きやすいです。
底材とレイアウト
- 土や腐葉土を2〜3cmほど敷くと落ち着きやすい。
- 観察を重視するならキッチンペーパーでも代用可能。
- 小さな木片や石を入れると隠れ場所になり、虫が安心します。
温度と湿度の管理
- 最適温度は25℃前後。夏場は直射日光を避け、冬は室温に注意。
- 乾燥しすぎると弱るので、霧吹きで1日1回軽く湿らせるのが理想です。
掃除のタイミング
フンや食べ残しは放置すると臭いやカビの原因になります。2〜3日に一度はチェックして、必要に応じて取り除きましょう。
環境を整えることで、虫たちは安心して鳴き、私たちも気持ちよく観察や音色を楽しむことができます。
エサと水分補給
虫たちが元気に鳴いてくれるかどうかは、日々の食事にかかっています。栄養と水分をしっかり与えることで、長く健康に育てることができます。
エサの基本
- 専用フード:市販の鈴虫・コオロギ用フードは手軽で安心。
- 野菜:きゅうりやナス、キャベツなどを少しずつ与えると喜びます。
- タンパク源:煮干しやかつおぶし、魚粉を少量加えると活発さが増します。
市販フードをベースにしつつ、野菜やタンパク源をプラスするのが理想的。毎日取り替えて、新鮮なものを与えましょう。
水分の与え方
- 水皿は溺れる危険があるため避けたほうが安心。
- 野菜の水分で補給できるので、きゅうりやナスは特におすすめ。
- 乾燥が気になるときは霧吹きで軽く湿らせるとよいです。
エサや水分の工夫で虫たちの鳴き声がさらに響き、観察も楽しくなります。
次は、繁殖や世代をつなぐ飼育方法について解説していきましょう。
世代をつなぐ育て方
鈴虫やコオロギを毎年楽しみたいなら、繁殖にもチャレンジしてみましょう。卵から次の世代を育てられると、飼育の喜びがぐんと広がります。
卵を産ませるコツ
- 鈴虫:湿らせた土に産卵します。秋の終わりに卵を残しておくと、冬を越して翌夏に孵化します。
- コオロギ:同じく土に産卵しますが、温度が25℃前後で保たれていれば数週間で孵化します。
卵の管理
- 鈴虫の卵は冬の低温を経て春に目を覚ますため、土ごと乾燥させすぎないよう注意します。
- コオロギの卵は乾燥に弱いので、湿度を保ちながら管理します。
孵化後の育て方
孵化した幼虫はとても小さく繊細です。最初はきゅうりや専用の粉末フードなどを細かく与え、徐々に大人と同じエサへ移行します。ケースも小さいものでスタートし、成長に合わせて広げていくと安心です。
卵から育てる体験をすると、鈴虫やコオロギの一生を通じて観察でき、より深く自然の営みを感じられます。
次は、鳴き声を楽しむ際の注意点や工夫についてまとめていきましょう。
鳴き声を楽しむための工夫と注意点
せっかく育てるなら、心地よく鳴き声を楽しみたいものです。そのために知っておきたいポイントを紹介します。
置き場所に注意
- 寝室に置くと夜中の鳴き声で眠れないことも。リビングや廊下などが安心です。
- 直射日光やエアコンの風が当たらない場所を選びましょう。
鳴きやすい環境作り
- オス同士を詰め込みすぎないこと。3〜5匹くらいがちょうど良いです。
- 適度な湿度と栄養バランスのとれたエサで健康を維持すると、よく鳴きます。
音色を楽しむ工夫
- 鈴虫とコオロギを一緒に育てて、鳴き声の違いを聞き比べてみる。
- 夜に灯りを落として静かに耳を澄ますと、より一層響きが感じられます。
ちょっとした工夫で、秋の夜を彩る「虫の音コンサート」を自宅で楽しめますよ。
まとめ
自宅で鈴虫やコオロギを育てるのは、思ったよりも手軽で楽しいものです。ポイントは次の通りです。
- 鳴き声を楽しみたいならオスを選ぶ。
- 広めで清潔なケースと適度な湿度を整える。
- 専用フードをベースに、野菜やタンパク源を加えて元気に育てる。
- 卵から世代をつなげば、毎年楽しむこともできる。
- 鳴き声を心地よく聞くためには、置き場所や環境を工夫する。
こうした基本を押さえることで、自宅でも秋の虫たちの音色を長く楽しめます。静かな夜に耳を傾ければ、自然と心が落ち着き、ちょっと贅沢な時間を味わえるでしょう。