幼稚園や保育園の入園準備で、多くのママ・パパが悩むのが「上履きの名前書き」です。
子どもが自分の靴をすぐに見つけられるようにするため、そして先生方が一目で分かるようにするために欠かせない作業。
でも実際に書いてみると「どこに書けばいいの?」「にじんでしまった」「何度洗濯しても消えない方法は?」など、ちょっとした困りごとが出てきますよね。
この記事では、そんなお悩みを解消できるように、上履きの名前をきれいに・分かりやすく・長持ちさせる方法をたっぷりご紹介していきます。
園のルールをまず確認
「名前はかかとに」「黒いペンで」「必ずひらがなで」など、園によってルールが決まっていることがあります。

先に確認しておかないと、せっかく書いたのに「もう一度書き直してください」と言われることも。
まずは配布資料や先生からの案内をよくチェックしておきましょう。
さらに、同じ地域でも園ごとに細かい違いがあり、「白いゴムの部分だけ使用する」「クラスカラーのテープを一緒に貼る」など独自ルールが設けられていることもあります。
特に初めてのお子さんを入園させるご家庭は、先輩ママや先生に直接尋ねると安心です。
よくあるルール例
- 白い部分に黒インクで記入する
- 苗字と名前をフルネームで
- 文字はひらがなで大きく書く
- 左右どちらにも必ず書く
- 園指定の色ペンやテープを使う
- クラスごとにシールやマークを併用することも
こうした決まりは園や学校によって違うため、周囲の先輩ママや先生に確認しておくと安心です。
また、指定に従うことで先生方の管理がスムーズになり、子ども同士の取り違えも防げます。
ルールを軽視せず、まずは基本を押さえることがきれいで長持ちする名前書きへの第一歩です。
上履きに名前を書くおすすめの場所
かかと部分

いちばん定番なのがかかとの後ろ側。下駄箱に入れた時に名前が見えやすく、先生もすぐに確認できます。
子ども同士で取り間違えることも少なくなります。
さらに、かかとは丈夫な部分なので摩擦で消えにくく、長期間はっきりと残りやすいのもメリットです。
園によっては「必ずかかとに書く」と指定されることもあるため、最初に選びやすい場所といえるでしょう。
また、かかとの外側と内側の両方に書いておけば、どの向きで置かれても見つけやすくなります。
甲(ゴム部分)

足の甲に当たるゴムの部分に書いておくと、上から見てすぐ分かるのがメリット。
子どもが自分の靴をパッと見分けやすい位置です。甲は履いた時にも見えるので、まだ字を読むのが苦手な子でも「ここに名前がある」という習慣がつきやすいのもポイントです。
さらに、ゴム部分は多少伸縮するのでインクが入りやすく、くっきりと書ける場合があります。
ただし摩擦が多い部分でもあるため、しっかりと布用のペンや専用スタンプを使うことが長持ちのコツです。
つま先や中敷き

つま先は摩擦で消えやすいですが、スペースが広いので書きやすいという声もあります。
デザイン的にも見やすく、正面から確認できるため「どっちが自分の靴か」が一目でわかる安心感があります。
ただし、遊びや運動でこすれることが多いので、シールやスタンプを組み合わせて補強すると安心です。
中敷きに補助的に書いておくと、混ざった時に「自分のだ!」と見分けやすい安心ポイントになります。
特に遠足や発表会などでたくさんの靴が並ぶときには、中敷きにもしっかり名前があると紛失防止につながります。
中敷きは洗い替え可能な場合も多いため、シールタイプを貼っておくのもおすすめです。
上履きの素材別アドバイス
キャンバス布タイプ
もっとも一般的。布用ペンでしっかり書けば長持ちします。
ただしにじみやすいので、軽く湿らせたり、下敷きをしてから書くと失敗しにくいです。
キャンバス布は通気性があるためインクが染み込みやすく、うっかりすると文字がぼやけてしまうことも。
失敗を防ぐためには、新聞紙や厚紙を靴の中に入れて安定させながら書くとよいでしょう。
また、濃色のキャンバス布の場合は白インクペンを使うとくっきりと見えます。
さらに、上から透明な保護スプレーを吹きかけることで洗濯後も消えにくくなります。
ビニールタイプ
表面がつるつるしているので油性ペンが定着しにくいです。
布用シールやスタンプを活用すると安心。特にビニール素材はインクが弾かれてしまうため、直接書くと「ポロポロ剥がれてしまった」という声も少なくありません。
おすすめは耐水性の名前シールや、ラベルを透明テープで上から保護する方法です。
スタンプを使う場合は、専用の速乾インクを利用すると定着が良くなります。
デザイン性を求めるならアイロン不要のシールや、防水対応のラベルを選ぶと長期間使えます。
メッシュタイプ
通気性が良い分、凹凸があるため書きにくいことも。
大きめの名前シールやワッペンを使うのが便利です。ペンで書くと線が途切れやすいので、どうしても見づらくなってしまいます。
そのため、布用テープやタグをメッシュ部分に縫い付けてから名前を書くときれいに仕上がります。
ワッペンならデザインも豊富で、子どもが自分の靴を見つけやすくなるメリットも。
さらに、メッシュ素材は洗濯後に乾きやすいので、剥がれ防止にしっかりアイロン接着することで長持ちします。
文字の書き方のポイント
フルネームで
同じ苗字の子がいるクラスも多いので、苗字と名前の両方を書いておくのが基本です。
名字だけだと間違える可能性が高いため、必ずフルネームで記入しましょう。
特に兄弟姉妹で通っている場合には必須です。
さらに、入園当初は子ども自身が自分の名前をしっかり認識するきっかけにもなります。
ひらがなで大きく
小さな子でも読めるように、ひらがな表記が安心。
小学校から漢字に変えるケースもありますが、園生活ではまず「読めること」が大事です。
大きめに書くことで遠くからも一目で分かりやすく、先生方の確認もスムーズになります。
また、濁点や小さい「ゃ・ゅ・ょ」なども見やすいように書くと良いでしょう。
はっきりと濃く
太すぎるとにじみやすいので、中細タイプの布用ペンがベストです。
線が薄いとすぐにかすれて読みにくくなるため、しっかりとインクがのるペンを選びましょう。
ペン先が丸いタイプは安定しやすく、力を入れなくても均一な線が書けます。
複数回なぞることでさらに濃さを出す方法も効果的です。
縦書き・横書きの工夫
ゴムの幅に合わせて縦書きにするなど、バランスを考えて配置すると美しく仕上がります。
靴のデザインによっては横書きの方が自然な場合もあるので、実際に置いてみて読みやすい配置を選ぶと良いです。
文字数が多い場合は小さめに分割して2段にするなどの工夫もできます。
さらに、色違いのペンを部分的に使ってアクセントを付けると、子どもが自分の靴を覚えやすくなる効果もあります。

文字の書き方ひとつで「にじみにくさ」や「見やすさ」が大きく変わります。少しの工夫を加えるだけで仕上がりが格段に良くなるので、時間をかけて丁寧に書くことを心がけてください。
にじまない&長持ちさせるコツ
名前書きでいちばん困るのが「にじみ」や「洗濯後の薄れ」。
これを防ぐにはちょっとした工夫が役立ちます。
きれいに仕上げるためには、書く前・書いた後の両方でひと手間加えることが大切です。
書く前の準備
書く前にアルコールティッシュで表面を拭き、汚れや油分を取ります。
特に新品の靴は製造時の加工剤が残っていることが多いので、拭いておくだけで定着がぐっと良くなります。
下処理でにじみ防止
にじみやすい布部分は、少し湿らせてから書くと安定します。
水を軽く含ませた布で表面をなでる程度で十分です。インクが急激に広がらず、細かい文字もきれいに出やすくなります。
書いた直後の工夫
書いた後にヘアスプレーで軽くコーティングして乾かすと、にじみや色落ちを防げます。
スプレーは20cmほど離して均一に吹きかけ、完全に乾いてから使用しましょう。
速乾性のあるタイプを選ぶと作業もスムーズです。
トップコートで補強
マニキュア用のトップコートを塗っておく方法も人気です。
特にかかと部分など摩擦の多い場所に塗ると長持ちします。
塗るときは薄く数回重ね塗りするのがコツです。
追加の工夫
アイロンで熱を加えるとインクの定着が良くなる場合もあります。
布用マーカーなら、あて布をして低温で軽く押さえるとさらに落ちにくくなります。
また、透明フィルムを貼って保護する方法もあり、洗濯を繰り返すご家庭にはおすすめです。

このように「準備・記入・仕上げ」の3段階で工夫を取り入れると、にじみにくく長持ちする名前書きが実現できます。
ペン以外の便利な方法
「字を書くのが苦手」「もっとおしゃれにしたい」という方には、こんなアイテムも便利です。
- 名前シール:アイロン接着タイプや防水・洗濯OKタイプがあり、貼るだけで完成。
- お名前スタンプ:布専用インクを使えば、ポンと押すだけで均一に仕上がります。大量に準備するときに便利。
- ワッペンや刺繍:かわいらしさ重視ならおすすめ。ただし園によっては不可の場合もあるので要確認です。
- マークやタグ:文字がまだ読めない子には、星やハートなどマークを加えると分かりやすいですよ。
子どもが自分の靴を見分けやすくする工夫
小さな子にとっては「自分の名前を読む」より「自分の印を見つける」方が簡単です。
名前にワンポイントを添えるだけでぐっと分かりやすくなります。
- 名前の横に☆や♡などのマークをつける。
- 兄弟姉妹がいる場合は、色違いのラインを入れて区別する。
- 左右の識別が難しい時期は、片方に色付きマークを描いて「こっちが右!」と分かるようにする。
体験談・あるある失敗談
- 「にじまないように太いペンを使ったら、逆に大きく広がってしまった」
- 「小さく書いたら、子どもが読めなくて『どっち?』と毎回聞かれた」
- 「洗濯したら一度で薄くなってしまい、慌ててシールを追加した」
- 「お下がりで使おうと思ったけど、名前が消えずに困った」
こうしたリアルな失敗談を知っておくだけでも、準備に役立ちます。
準備のタイミングと注意点
- 上履きを購入したら、使う前に必ず名前を書いておく。
- 入園直前は忙しいので、早めに記名を済ませておくと安心です。
- 書くときは新聞紙やビニールを敷いて、乾燥させてから収納しましょう。
- 予備の上履きにも同じ方法で記名しておくと、急な洗い替えに便利です。
よくある失敗とその対処法
- にじんでしまった → 布用ペンに変えるか、マスキングテープの上から書いて保護する。
- 洗濯で薄れた → コーティングスプレーを使うか、スタンプやシールに切り替える。
- 間違えて書いた → 除光液で消せる場合もあるが、布を痛めやすい。上からシールを貼るのが安心。
- シールが剥がれた → アイロンで再接着するか、新しいものに貼り替えましょう。
Q&Aコーナー
Q. 名前を消したいときはどうすればいい?
A. 除光液や漂白剤で落とせることがありますが、生地を傷めやすいので注意。上から新しいシールを貼る方が無難です。
Q. 下の子にお下がりとして使いたい場合は?
A. 上書きは見づらくなるため、なるべくシールやタグを使って取り替えできる方法にしておくのがおすすめです。
Q. ペンとシールはどちらが長持ち?
A. ペンはシンプルで薄くなっても書き直し可能。シールはデザイン性が高いですが、洗濯で剥がれることがあるので、両方を組み合わせて使うのがベストです。
まとめ
上履きの名前は「見やすく・にじまない・取れない」が大切です。
基本はかかとと甲の2か所に、ひらがなでフルネームをはっきりと。ペンだけでなくシールやスタンプを上手に使えば、誰でもきれいに仕上げられます。
さらにワンポイントを加えれば、子どもが自分の靴をもっと見つけやすくなります。
準備のタイミングや工夫を押さえておけば、入園後も安心して過ごせます。
入園準備の一歩として、ぜひ余裕を持って取りかかってくださいね。
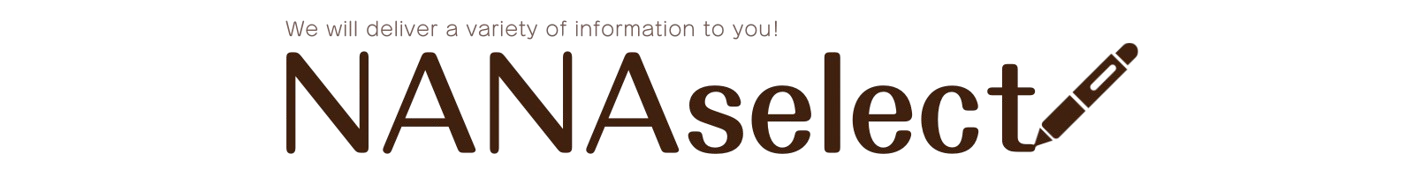

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1b1e9275.8171176e.1b1e9276.884b2b50/?me_id=1257130&item_id=10000320&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fzeetop%2Fcabinet%2Fk-mini%2F03156594%2Fnormal8.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)


