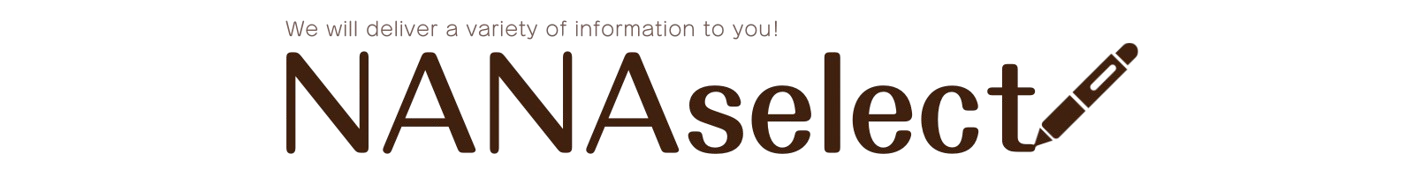「シシトウを食べたら、たまたま辛いのが混じっていてびっくりした」という経験、ありませんか?
スーパーで買っても、自分で育てても、普段は優しい甘みなのに、時折“ピリッ”とするものがあります。
これはシシトウの特徴とも言えますが、家庭菜園ではできるだけ辛さをコントロールして“はずれ”を減らしたいものです。
本記事では、シシトウが辛くなる原因や“辛い実”の見分け方、さらに育てる際に辛味を抑える栽培の工夫を、詳しく解説します。
そもそも、なぜ“辛いシシトウ”ができるのか?

- 品種・遺伝的な要素
シシトウは基本的には辛味をほぼ持たない品種ですが、「辛い実」が少数混じることが知られています。これは遺伝的な特徴によるもので、どんなに同じ条件で栽培しても数%程度は辛い実が混ざる可能性があります。種のロットや育った環境によっても差が出るため、完全に避けることは難しいのです。 - 環境ストレス
高温・乾燥・強い日差しなどで植物がストレスを受けると、カプサイシン(辛味成分)が増加することがあります。特に真夏に水やりが不足したり、強い日差しにさらされた場合は辛味が強まる傾向があります。風通しの悪い環境や根詰まりもストレスとなるため、鉢植え栽培では注意が必要です。 - 成熟度(採る時期)
完熟に近づくと辛味が強くなることがあります。緑色のうちに収穫すると辛味は抑えられる傾向です。逆に収穫を遅らせて赤くなるまで放置すると、辛味がはっきりと出る場合があります。家庭菜園では実の大きさが揃った頃に早めに収穫するのが安心です。 - 土壌の養分・肥料バランス
肥料不足や水不足などもストレスとなり、辛味が強まる原因になります。特にチッソ不足は生育不良を招き、株全体が弱って辛味が出やすくなると言われています。一方で肥料を与えすぎても根が傷み、結果的にストレスとなるため、適度なバランスを保つことが重要です。
辛い実を見分けるポイント

| 見分けポイント | 辛さが出やすい兆候 | 注意点・例外 |
|---|---|---|
| 形 | 先端が細く尖ったり、細長い実は辛味が出やすい | 見た目だけでは確実ではない |
| 色・ツヤ | 表面が濃い緑で光沢が強い実は辛味の可能性あり | 色ムラだけで判断はできない |
| 収穫タイミング | 若採りは辛味少なめ、熟すと辛味が増しやすい | 熟度によって風味も変化 |
| 大きさ | 小ぶりで皮が薄めの実は辛味が出やすい | 厚みがあっても辛い場合もある |
辛くならないように育てる栽培方法

土と肥料
- 水はけの良い土を用意し、堆肥や腐葉土で改良する。赤玉土やバーミキュライトなどを混ぜると通気性・排水性がさらに良くなる。
- 土のpHはおおよそ6.0~6.8が適切。酸性が強すぎると根が養分を吸収しにくくなるので、苦土石灰で調整するのもおすすめ。
- 花期~結実期にはリン酸・カリをやや多めに与える。リン酸は花つきを良くし、カリは実を充実させる。液体肥料を週1回程度与えると安定して育ちやすい。
- 元肥に緩効性肥料を混ぜておき、追肥として定期的に与えると効果的。肥料切れを防ぐことでストレスが減り、辛味の発生を抑えやすい。
水やりと環境管理
- 乾燥しすぎはNG。夏場は朝夕の水やりを心がける。特に鉢植えは土が乾きやすいため注意する。
- 猛暑時は遮光ネットを使って強い日差しを和らげる。遮光率30%程度のものなら日照不足になりにくい。
- 株間を広く取り、風通しを良くすることで病気や害虫も防ぎやすい。地植えなら40cm程度の間隔を空けるのが目安。
- マルチングをして地温や水分を一定に保つのも有効。ワラや黒マルチを使えば雑草防止にもなる。
株管理と収穫
- 若いうちに収穫すれば辛味が少ない。緑色でつやのあるうちに収穫するのがおすすめ。
- 完熟させると甘みは増すが辛味も出やすい。赤くなった実は彩りに利用できるが、辛味リスクが高いことを意識して使う。
- 辛さが出にくい品種を選ぶのも効果的。タネ袋に「辛味が少ない」と記載された品種を選ぶと安心。
- 不要なわき芽は取り除き、株全体の栄養を実に集中させる。病気の葉や黄変した葉は早めに摘み取り、株を健全に保つことも大切。
“辛いシシトウ”を完全に防ぐことは可能か?

「辛いシシトウ」を100%防ぐのは難しいのが実情です。理由は以下のとおりです。
- 遺伝的にごく少数で辛味が出る実が混じることがある。これはシシトウの品種が持つ特性のため、栽培条件をどれほど整えても完全には排除できません。
- 気温や湿度など、自然条件は完全には制御できない。特に日本の夏は高温多湿となりやすく、土壌の乾燥と急な豪雨が繰り返されることで植物に大きなストレスがかかります。その結果、カプサイシンが増加し辛味のある実が生じることがあります。
- 株ごとの個体差で辛味が偏ることもある。健康に見える株でも、根の張り方や日当たり、肥料の吸収具合の違いによって辛い実が多く出る場合があります。同じ畑やプランターで育てても「この株だけ辛い」ということが起こり得るのです。
- さらに、栽培者が収穫のタイミングを逃して実が熟しすぎたり、剪定不足で株が蒸れたりすると、それもストレス要因になり辛味を強めることがあります。つまり環境・管理・遺伝の三つが絡み合って“辛い実”が生まれるのです。
こうした理由から、完全に防ぐのは不可能ですが、適切な管理を徹底すれば辛い実の割合をぐっと減らすことは可能です。
辛い実が混ざった時の対処法

- 収穫後に小さく切って味を確認する。辛いものを見つけたら調理に混ぜる量を減らし、辛さの偏りを避ける。
- 砂糖やみりん、酢などを使い、辛味を和らげる調理をする。甘味や酸味は辛味を中和しやすく、煮物や炒め物に加えると食べやすくなる。
- 緑色のうちに使うことで辛さを抑えられる。赤く熟したものは辛い可能性が高いため、彩りに使う場合は少量にとどめると安心。
- 焼き・揚げ調理で香ばしさを加えると辛味が感じにくくなる。天ぷらや素揚げ、グリルにすると風味が増し、辛さが和らぐことが多い。
- 辛い実を細かく刻み、薬味やピクルスとして活用する方法もある。辛味を料理全体に分散させれば、ピリッとしたアクセントとして楽しめる。
- 万が一強烈に辛い実を食べてしまった場合は、水よりも牛乳やヨーグルトなど乳製品を口にすると辛さが落ち着きやすい。カプサイシンは脂溶性のため、乳脂肪分が有効に働く。
- 辛さを避けたい場合は、調理前に種とワタを取り除くとさらに安心。辛味成分は種周辺に多く含まれるため、下処理で軽減できる。
まとめ

- 辛い実は「形・色・大きさ」である程度見分けられる。
- 栽培では「水・肥料・日照管理」でストレスを避けることが重要。
- 収穫を早めに行うと辛味を減らしやすい。
ちょっとした工夫で、“ほとんど辛くないおいしいシシトウ”を楽しむことができます。