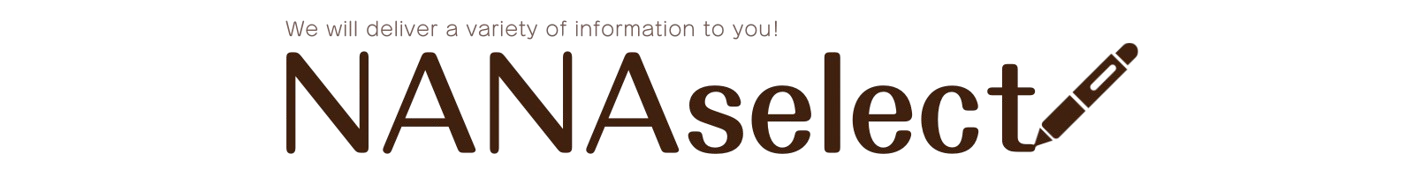じゃがいもの収穫、遅れるとどうなる?
腐敗や芽出し、保存性のリスクまで、見落としがちなポイントと適期の目安をまとめました。
じゃがいもの収穫、遅れるとどうなる?

じゃがいもの収穫時期を逃してしまうと、どんな影響が出るのでしょうか?
結論から言うと、「品質が落ちる」「保存しにくくなる」「腐る可能性がある」など、いくつかのリスクがあります。
特に家庭菜園では、「まだ土の中で育ってるかも」「あと数日で大きくなるかも」と思って収穫を先延ばしにしてしまいがち。
でも、その判断が裏目に出てしまうこともあるんです。
- 中が空洞になる(空洞症)
- 表面が割れてしまう(裂開)
- 長雨や梅雨によって土の中で腐ってしまう
- 芋に芽が出て栄養が失われ、味が落ちる
- 保存性が悪くなる(収穫後すぐに悪くなる)
こうしたトラブルは、収穫が遅れたことで起きやすくなります。
また、地上部が完全に枯れても、地中の芋は時間とともに劣化していきます。収穫が遅れるほど、「掘ったら腐っていた」「柔らかくなっていた」という残念な結果になることも…。
もちろん、2~3日遅れるくらいなら問題にならないこともあります。
ただし、雨が続く時期や猛暑が迫っている時期に収穫がずれると、急激に芋の状態が悪化することもあるので要注意です。
「少しぐらい大丈夫だろう」が命取りになるかもしれません。
では、じゃがいもはいつ収穫するのがベストなのでしょうか?
次は、「収穫の適期」の見極め方を具体的にご紹介します。
収穫の適期はいつ?見極めポイントをチェック

じゃがいもは、収穫の「ベストタイミング」がとても重要です。早すぎても未熟なまま、遅すぎても品質が落ちてしまいます。では、どうやって見極めれば良いのでしょうか?
ポイントは大きく分けて3つあります。
1. 葉や茎が黄色く枯れ始めたころが目安
じゃがいもの地上部(葉や茎)が青々としているうちは、芋はまだ成長中です。
反対に、葉が全体的に黄色くなり、茎も倒れ始めてきたら、それは「そろそろ収穫の合図」。
目安としては、半分以上の葉が黄色くなった頃に収穫すると、芋がちょうどよく育っていることが多いです。
2. 植え付けから約100日前後(品種による)
春植えの場合、植え付けからおよそ90〜110日後が収穫適期とされています(男爵やメークインなどの一般的な品種)。
ただし、品種によって生育期間に差があるので、種芋の袋やカタログなどで確認しておくと安心です。
3. 梅雨入り前 or 晴れた日の午前中に収穫が理想
収穫に向いているのは、梅雨入り前の晴れた日。晴れの日が数日続いて、土が乾燥しているときが良いです。
湿った土の中に長く置いておくと、病気や腐敗の原因になるため、できるだけ乾いたタイミングで収穫しましょう。
午前中に収穫して、そのまま風通しのいい場所で数時間乾かすのがベスト。これにより、土を落としやすくなり、保存性もアップします。
🌱 ワンポイント:掘る前に1株だけ試してみるのも◎
一度に全部掘らずに、まずは1株だけ試し掘りしてみましょう。
芋の大きさや皮の状態、全体の育ち具合を見て判断すると、失敗しにくくなります。
次は、収穫が遅れた場合の「味・保存・安全性」に関するよくある疑問を、Q&A形式でご紹介します。
「ちょっと遅れちゃったけど大丈夫?」という方も、安心して読める内容にしていきますね。
収穫が遅れたときのQ&A|味・保存・食べられる?

「うっかり収穫が遅れてしまった…」「雨が続いて掘れなかった…」
そんなとき、気になるのは「このじゃがいも、食べられるの?」ということですよね。
ここでは、収穫が遅れた場合によくある疑問にお答えします!
Q1:収穫が遅れても食べられるの?
はい、基本的には食べられます。
ただし、長く地中に放置されていたことで以下のような状態になっている可能性があります。
- 芋の皮が厚くなっている
- 芽が出てきている
- 一部が柔らかくなっている or 腐っている
- 味や食感が落ちている
特に気温が高い時期や雨が続いた後などは、傷んでいる芋が混ざっていることもあります。
掘り出したら必ずよく確認し、腐っている部分や芽の出ている部分は取り除いてから調理してください。
Q2:保存はできる?
収穫後すぐに芽が出やすくなっているため、長期保存には向かないことがあります。
なるべく早めに使い切るのがおすすめです。
保存する場合は以下の点に注意しましょう。
- 直射日光を避けて、風通しの良い冷暗所に置く
- 芽が出ていないか、定期的にチェック
- 湿気が多いと腐りやすいので新聞紙に包むなどして乾燥気味に保つ
Q3:食べるときに注意することは?
じゃがいもには「ソラニン」という天然毒素が含まれています。
収穫が遅れて緑色になった部分や芽が大きくなった部分にはこのソラニンが多く含まれるため、必ず取り除いてから調理してください。
- 緑色の皮 → 厚めにむく
- 大きな芽 → 根元までしっかり取る
こうしたポイントを押さえれば、多少収穫が遅れても問題なく食べることができます。
次のセクションでは、実際に「収穫が遅れてしまった」家庭菜園経験者の声を紹介しながら、どんな工夫や失敗があったのかを見ていきます。
実際に収穫が遅れた体験談から学ぶこと

収穫が遅れたらどうなるのか…それを一番よく知っているのは、実際に育てた人たちの声です。
ここでは、家庭菜園を楽しんでいる方々の体験談をもとに、「どんな失敗があったのか」「どう工夫して乗り切ったのか」をご紹介します。
◆ 体験談1:梅雨に入ってから掘ったら、一部が腐っていた…
→ 雨の後は要注意!
湿った状態で長く放置されると、じゃがいもは一気に劣化してしまうことがあります。
◆ 体験談2:芋が大きくなりすぎて割れてしまった!
→ 大きければいいとは限らない!
じゃがいもは、育ちすぎると割れたり中がスカスカになることもあります。適度なサイズ感を狙うのがベストです。
◆ 体験談3:遅れても大丈夫だった!という声も
→ 必ずしも失敗するとは限らない!
環境や品種によっては、少し遅れても大きな問題が出ないケースもあります。ただし、これはあくまで“たまたま”の成功だったかもしれません。
🔍 体験談からわかること
- 遅れるリスクは「雨・高温・過熟」によって大きく変わる
- 土の水はけや気候によって結果が違う
- 少しの遅れならセーフなこともあるが、基本は早めに掘る方が安心
次は、収穫で失敗しないために押さえておきたい「5つのポイント」をまとめてお伝えします!
じゃがいもの収穫で失敗しないためのポイント

じゃがいも収穫のタイミングを見極めるのは難しいですが、ちょっとしたコツを押さえておくだけで、失敗のリスクをぐっと減らせます。
ここでは、収穫で後悔しないために知っておきたい5つのポイントをご紹介します。
1. 地上部の状態をよく観察する
収穫適期を知らせてくれるのは「葉や茎の状態」です。
緑のままでは早すぎ、完全に枯れすぎると遅すぎ。
半分以上の葉が黄色くなったら目安と考えて、見逃さないようにしましょう。
2. 天気予報をチェックして「晴れの日」に収穫する
収穫は、できれば晴れた日の午前中に。
雨の後は土が湿っていて、収穫時に芋を傷つけやすく、腐敗の原因にもなります。晴れた日が数日続いて、土が乾いているときが良いでしょう。
雨が続きそうなら、少し早めでも掘ってしまう方が安心です。
3. 1株だけ試し掘りをしてから判断する
「そろそろかな?」と思ったら、まず1株だけ掘ってみましょう。
芋の大きさ、皮の状態、中身の様子などをチェックして、全体の収穫時期を見極めると失敗が少なくなります。
4. 掘ったあとはしっかり乾かす
掘ったばかりのじゃがいもは水分を多く含んでいます。
風通しの良い日陰で2〜3時間ほど乾かしてから保存すると、長持ちしやすくなります。
濡れたままビニール袋などに入れると、すぐに傷むので注意!
5. すぐに食べきれないときは、保存環境を整える
長期保存にはちょっとしたコツが必要です。
- 直射日光を避け、新聞紙に包んで冷暗所へ
- 芽が出てきたら早めに取り除く
- 定期的に状態を確認する
特に、収穫が遅れた芋は傷みやすいことが多いので、保存前にしっかりチェックすることが大切です。
この5つのポイントを意識すれば、じゃがいもの収穫はきっと成功に近づきます。
まとめ:早すぎても遅すぎてもNG!

じゃがいもの収穫は、「早すぎてもダメ、遅すぎてもダメ」。
ちょうどよいタイミングで掘ることが、美味しくて保存にも向いたじゃがいもを手に入れるためのポイントです。
今回の記事でお伝えしたように、収穫が遅れると…
- 芋が割れたり、空洞ができたりする
- 雨にあたって腐ってしまう
- 芽が出てきて栄養が落ちる
- 保存性が悪くなる
とはいえ、収穫の適期を正確に見極めるのは意外と難しいもの。
そんなときは、葉や茎が半分くらい黄色くなった頃を目安にしてみてください。
また、「そろそろかな?」と思ったら、まずは1株だけ試し掘りしてチェック!
天気予報も確認し、晴れた日に収穫することで、状態の良いじゃがいもを手に入れやすくなります。
掘ったあとはしっかり乾燥させてから保存。芽が出てきたら早めに使い切るなど、少しの工夫で美味しさを長く保てます。
手塩にかけて育てたじゃがいも。
「よし、ベストなタイミングで掘ったぞ!」と満足できるように、収穫時期の判断を楽しみながら行ってくださいね。