「もう遅いかな…」と思いがちな8月中旬の種まきですが、冷涼な地域でも、まだ間に合う可能性があります。
成功のカギは品種選びと栽培方法。
早生〜中早生で遅まきに対応しやすい品種を選び、発芽・初期生育を助ける管理をすれば、地域やその年の気象によりますが、11月下旬〜12月ごろの収穫も十分に狙えます。
この記事では、
- 冷涼な気候でも育てやすいおすすめ品種
- 発芽を安定させる「厚播き(やや密に条播き)」のコツ
- 間引きスケジュール
はじめての方にも分かりやすくご紹介します。
では、なぜ8月中旬からでも間に合うのか、その理由を見ていきましょう。
8月中旬からでも人参は間に合うの?
「お盆を過ぎたらもう無理かな…」と思う方も多いですが、早生〜中早生の品種を選べば、冷涼な地域でも8月中旬播種で11月下旬〜12月ごろの収穫は十分可能です。
- 早生品種は播種からおよそ90〜110日で収穫可能
- 秋の冷え込みで糖度が高まり、甘みが増す
- 晩生(おくて)品種は寒さが来る前に肥大が間に合わないことがあるため不向き
特に冷涼地の秋は、日中の適温と朝晩の冷え込みが組み合わさり、人参の生育に理想的な環境が整います。
そのため、適切な品種選びと管理を行えば、お盆過ぎでも美味しい秋冬どりの人参が育てられます。
次は、8月中旬からの播種におすすめの品種をご紹介します。
遅まきにおすすめの人参品種
ひとみ五寸
冷涼地での遅まきに特におすすめなのが、カネコ種苗のひとみ五寸です。
夏まき冬どり向けに育成された品種で、播種後およそ110日で収穫可能。低温下でも肥大性が高く、太く甘い根に育ちます。
- 青首や肩割れの発生が少ない
- 黒葉枯病に強い
- カロテン含量が高く、甘みも強い
冷涼な気候や標高の高い場所でも、遅まきで収穫が間に合う可能性が高い品種です。
時無五寸
「時無(ときなし)五寸」は早生タイプで幅広い時期に播種できる定番品種です。
四〜五寸タイプで、収穫までは110〜130日が目安。ただし冷涼地では、遅まきの場合に寒さが来る前に太り切らないこともあります。
その他の早生品種
- ベータリッチ:カロテン含量が高く、早生で播種後90〜100日で収穫可能。甘みがあり、家庭菜園でも育てやすい。
- 恋ごころ:夏まき〜秋冬どり向けの五寸系。根色や形が良く、遅まきでも肥大性が高い。
いずれの品種も、播種時期とその後の管理次第で結果が変わります。
次は、発芽を安定させて苗の質を高める「厚播き」のコツをご紹介します。
厚播きで発芽率と苗の質を上げる

ニンジンは発芽率がやや低く、乾燥にも弱い作物です。
特に真夏の種まきでは、種をまいても思うように芽が揃わないことがあります。そんなときに有効なのが「厚播き(あつまき)」です。
厚播きとは、やや密に種をまく方法のこと。
厚播きのやり方
- 条播きで1cm間隔を目安にパラパラと種をまく
- 覆土は3〜5mm程度(好光性種子のため厚すぎない)
- まき終わったらたっぷり水を与え、不織布や新聞紙で軽く覆って乾燥を防ぐ
間引きスケジュール
- 本葉1枚の頃:株間を2〜3cmに間引く
- 本葉3〜4枚の頃:株間を8〜10cmに間引く
厚播きは発芽を安定させるだけでなく、後の間引き作業で生育の良い株を選べるという利点もあります。
次は、冷涼地で8月中旬にまいた場合の栽培カレンダーをご紹介します。
冷涼地・8月中旬播種の栽培カレンダー例
ここでは、冷涼な地域で8月中旬に人参をまいた場合の、一般的な栽培スケジュール例をご紹介します。天候や土壌条件によって前後しますが、おおまかな目安として参考にしてください。
| 時期 | 作業内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 8月中旬(播種) | 条播き+厚播き、覆土3〜5mm、水やり | 乾燥防止のため不織布や新聞紙で軽く覆う |
| 8月下旬〜9月上旬(発芽) | 発芽確認、適度な潅水 | 芽が揃うまで乾燥させない |
| 9月中旬(1回目間引き) | 本葉1枚で株間2〜3cmに調整 | 生育の良い株を残す |
| 10月初め(2回目間引き・追肥・土寄せ) | 本葉3〜4枚で株間8〜10cmに調整 | 肩が日光に当たらないよう土寄せする |
| 11月下旬〜12月初め(収穫) | 根径4〜5cmになったら収穫 | 寒さが厳しくなる前に早めの収穫を |
このスケジュールを目安にすれば、8月中旬まきでも甘くて太い人参を収穫できます。
次は、失敗を防ぐための注意点をご紹介します。
失敗しないための注意点
間引きはタイミングが命

間引きが遅れると、根が細くなったり形がいびつになったりします。特に冷涼地では生育期間が限られるため、本葉1枚・本葉3〜4枚の時期を逃さずに間引きましょう。
発芽期の乾燥防止

もみ殻でもOK
発芽期は土の表面が乾くと一気に発芽率が下がります。播種後は不織布や新聞紙で軽く覆い、発芽が揃うまで適度な潅水を続けましょう。
青首を防ぐ土寄せ

根の肩が日光に当たると緑色になり、品質が落ちます。2回目の間引きの際に、株元に土を寄せて光を遮りましょう。
寒さ対策

11月以降、最低気温が一桁になる頃は、不織布やビニールトンネルで保温すると肥大が進みやすくなります。特に遅まき分は低温での成長が鈍りやすいため、有効な方法です。
これらのポイントを押さえれば、8月中旬まきでも高品質な人参を収穫できます。最後に、今回の内容をまとめましょう。
まとめ
冷涼な地域でも、8月中旬からの人参栽培は品種選びと管理次第で十分に可能です。
早生〜中早生の品種を選び、厚播きや間引き、乾燥防止などの基本を押さえることで、11月下旬〜12月初めには甘くて太い人参が収穫できます。
- 早生・遅まき対応の品種(例:ひとみ五寸、スカーレットナント、ベータリッチ)を選ぶ
- 発芽率を高めるために厚播き+覆土3〜5mm
- 間引き・土寄せ・追肥のタイミングを守る
- 寒さが早く来る地域では不織布やトンネルで保温
冷涼地の秋は、昼夜の寒暖差によって糖度が高まり、人参の甘みが増す絶好の季節です。
播種のタイミングが遅めでも、今回ご紹介したポイントを実践すれば、美味しい秋冬人参を楽しむことができるでしょう。
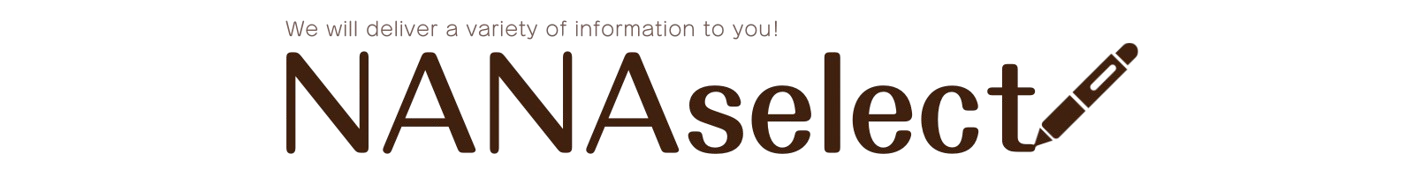

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b2e1239.7dbeedd3.4b2e123a.9dc4a5e3/?me_id=1411559&item_id=10000463&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fatelier-plum%2Fcabinet%2Fcompass1721799353.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b2e17ea.0adec448.4b2e17eb.a0394f4f/?me_id=1228070&item_id=10003248&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyorozuya-souko%2Fcabinet%2Fyasai%2Fimg60837289.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b2e2e02.9e1796c8.4b2e2e03.fea1cd39/?me_id=1251188&item_id=10000130&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyonezawa%2Fcabinet%2Ftane01%2F1015ninjin%2Fbetarich.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b2e2b19.5155cace.4b2e2b1a.04925340/?me_id=1339292&item_id=10014617&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftanehyo%2Fcabinet%2F05401539%2Ftakiisyubyo%2Ft-tki-nnz-493-a.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

